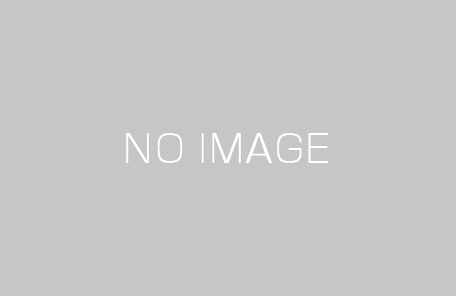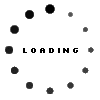教会の主であるイエス・キリストが、けさここに席を整えて私たち一人ひとりを待っていてくださいました。そして詩編133編1節の、「見よ、兄弟が共に座っている。なんという恵み、なんという喜び」という呼びかけをききました。それぞれ私たちは違う人間ですが、そのままの違いをもちながら、また違いをだいじにしながら、恵みと喜びの席に着いている不思議さをおぼえます。
昨日2月11日は、この日本では「建国記念の日」でした。この日が制定されてから50年ほどになります。制定をめぐっては多くの問題がありましたが、多くの人々は国に誕生日があってもいいとか、国民の休日が増えて仕事や学校が休みになるとか、そういうポピュリズムの気運の中では歴史的議論とはならず、また国会での決議もなく、政府の一方的な政令で制定されました。しかし、心ある市民たちや宗教者や団体、そしてキリスト教会は深く憂慮しました。何が問題であったかというと、その日が2月11日であったからです。戦争が終わるまでの日本は、二千六百年前に天皇の祖先が神として天降った日として神話から2月11日を割り出し、この日を紀元節と名づけて国の最も重要な記念日としていたのです。
紀元節について、小学生の時の体験を少し紹介します。この日、寒い講堂には全校生徒が集まり、式が行われました。式に先立って、校長室から天皇の写真と教育勅語の巻物が校長と教頭によって恭々しく運ばれてきます。生徒たちは厳粛に待ちます。正面講壇に安置されると、一同は君が代を歌い、勅語の朗読を聞き、校長の訓話を聞きます。その内容は、天皇の祖先は天から降った神であること、その子孫である天皇も現人神(アラヒトガミ)であること、現在、日本はアメリカとイギリスと戦争をし、多くの日本の兵隊は命を惜しまずに戦っているが、この戦争は神である天皇がお決めになったのだから、必ず勝つこと、など毎回同じものでした。最後に、紀元節の歌をうたいます。その歌は体に染みついていて、今でも歌えます。小学校4年まで紀元節の式を体験しましたが、それはまるでキリスト教会の礼拝のようでした。またこういうこともありました。もし写真や勅語を運ぶ途中で落としたり、読み間違えでもすれば、校長や教頭は責任を問われ、そのため自殺した校長は、その責任感の強さを誉められたほどです。このような雰囲気の中で、当時の人々の思想や宗教がどんなに窮屈な状況に置かれていたか、想像していただけると思います。
戦争が終わって天皇は「私は神ではない」と宣言し、新しい憲法ができ、だれもが自由に宗教を選び信仰を持つことができるようになりました。いわゆる信教の自由です。それなのに20年も経つと、かつての2月11日の紀元節が復活しました。ただ表面的に名前が変わっただけです。もちろん以前のような紀元節行事は学校では行なわれないにしても、その精神は残されたままです。そこでこれを憂慮する日本の教会は、この日を信教の自由を守る日として、祈りと行動を続けてきました。
ところで、教会の執事会から信教の自由ということでメッセージを依頼されたとき、まず頭に浮かんだのがガラテヤの信徒への手紙でした。そこには「神は人を分け隔てなさらない」とか「そこではもはやユダヤ人もなくギリシア人もなく、奴隷も自由な身分の者もなく、男も女もありません」とか、さらに「この自由を得させるために、キリストは私たちを自由にしてくださった。だからしっかりしなさい。だから二度と奴隷の軛につながれてはなりません」などの文章があるからです。
現在、世界のあちこちで戦争が起こり、または戦争前の状況にあります。その原因や理由は複雑ですが、現象的には、民族と民族や人種と人種との対立となってあらわれ、それに宗教と絡み合う様相を呈しています。すでにヨーロッパの先進国の右翼の台頭による民族主義、米国トランプ大統領の白人優位の人種主義などが起こり、そのような動きは足元の日本でも単一民族観やヘイトクライム(中国や北朝鮮・韓国の蔑視)にあらわれ、人々を不安に駆りたてています。そのような中で、イエス・キリストの福音によって建てられている教会はどう考え、平和への祈りを言葉にするのか、大きな課題です。しかしこれらの問題は、新約聖書の問題でありました。ユダヤの一隅に起こったイエス・キリストの福音が、どのようにしてユダヤの民族主義や人種主義の枠を乗り越え、世界的に広がっていったのかを描いているからです。ガラテヤの信徒への手紙を取り上げたのは、これらの問題を教会の課題として展開しているからです。
ガラテヤの信徒への手紙、以後ガラテヤ書と呼びますが、書き手はパウロです。このパウロは、主イエスの直弟子たちとは違い、ユダヤから遠い外国の地で生まれ、異国の伝統や文化の中で生きたユダヤ人です。ですからパウロは、ユダヤ人であることをあまり自覚せずに当たり前のこととして生きてきたペトロらとは違い、自分がユダヤ人であることを意識し、ユダヤ人であろうとしたユダヤ人でした。パウロはユダヤ教の中心であるエルサレムに留学し、ユダヤ教の教えである律法を習得し、その証しとして、当時ユダヤ教の周辺でイエスの福音宣教をするキリスト教徒を、ユダヤ教の律法に反するものとして排除する運動に加わります。ところがキリスト教徒をとらえエルサレムに連行するためにシリアのダマスコに向かう途中、パウロは復活のイエスに出会い、そのイエスに向き合い、そこで全く新しくされます。パウロにとっては思いがけない青天の霹靂であり、目からうろこが落ちるという表現が生まれたほどです。使徒言行録が伝えるこの出来事を、パウロの回心と言いますが、それ以来パウロは、キリストの福音を伝える者へと変えられました。パウロ自身もそれを、先ほど読んだ3章23節では「啓示」、つまり神が起こされた不思議な出来事と言っています。
こうしてパウロは、ユダヤ教、外国つまり異邦の宗教、そしてキリスト教という三つの異なる世界に生き、そこに身を置き、悩み苦しみ、その緊張関係の中でキリストの福音を考えぬき、語り続けた人といえます。さきほど述べた「神は人を分け隔てなさらない」とか「そこではもはやユダヤ人もなくギリシア人もなく、奴隷も自由な身分の者もなく、男も女もありません」というパウロの言葉は、それぞれの違いを受けとめ、それらをつなぎ、共に神の国への道を歩もうとする教会の現場から出てきたものです。
けさ与えられている聖書箇所の2章15節以下を読んでいきましょう。
16節でパウロは、こう言います、「人は、イエス・キリストへの信仰によって義とされると知って、私たちもキリスト・イエスを信じました。」ここでイエス・キリストへの信仰とは何でしょうか。私には若いころからわかりにくい言葉でした。教会の説教などで、信仰が深いとか浅いとか、熱心だとか冷たいとか、健全だとかそうでないとか、そういう言い方を耳にすると、信仰は人間次第のこととして聞こえ、私は自分の居場所がなくなり、礼拝後も心穏やかではありませんでした。神学校時代も同じ思いが続いていたのですが、新約聖書のもともとの言葉を習い覚えてからこの「イエス・キリストへの信仰」という語句に触れたとき、ああそうだったのかと目からうろこが落ちるような体験をしました。その言葉を日本語にそのまま置き換えると「イエス・キリストの信仰」あるいは「イエス・キリストの信実・誠実」ということになります。もともと私は単純な人間ですから、そのままの置き換えでしか考えられない。ところが、「イエス・キリストへの信仰」とか「イエス・キリストを信じる信仰」という訳になると、信仰とは人間こちら側のこととなってしまう。おそらく読者が理解しやすいようにとの翻訳者の親切心でしょうが、親切の行き過ぎが真意をずらすことになる。そう気づいたとき私は、イエス・キリストの人に対する誠実・信実こそが人を義とするのだ、つまり救うのだと受け取りました。将来に不安な気持であった私は、それさえ語ればよいのだと得心し、牧師の道が開かれました。まさにそれは「目からうろこ」でした。
もう少しパウロについて考えましょう。
先ほどの繰り返しになりますが、使徒言行録の著者であるルカは、パウロはキリスト教徒迫害の途上で復活のイエスに出会い、キリストの福音伝道者になったと伝えています。パウロは、その不思議な出来事について自分の文章では触れていませんが、ガラテヤ書1章12節では「人から受けたり教えられたりしたのでなく、イエス・キリストの啓示による」と述べます。パウロは何を啓示され、何を見たのでしょうか。復活のイエスとパウロの出会いはその第三者である後代の歴史家ルカによる記述ですが、ではパウロ自身の言葉ではそれはどういうことであったのでしょうか。ガラテヤ書3章1節は、パウロがガラテヤ教会に対して自分たちの信仰がどこから始まったのか、その原点を確かめようとする件(くだり)ですが、こう言っています、「あなたがたは、目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきり示されたではなかったのか!」かつてパウロはガラテヤ教会で、十字架の主イエスを繰り返し語り続けていたのでしょう。
ではパウロは、主イエスの十字架をどのように語っていたのでしょうか。パウロは、イエス・キリストの十字架に向き合ったとき、そこに律法で生きようとする自分自身の姿が重なり、主イエスと共に磔にされて死んでいる自らの姿をみたのでした。それまでパウロは、神に選ばれたユダヤ民族の一員であることを誇りとし、そこに生きがいを感じて努力精進していたのですが、パウロが見たものは、ユダヤ人としての誇りと共に十字架につけられた自分の死の姿でした。しかしそのイエスは復活して生きておられる。自分もこのように生きている。パウロはその自らの現実をそのまま受けいれたのです。
そのパウロが、後日の文書であるローマの信徒への手紙で、こう言っています。少々長くなりますが読みます。
ローマの信徒への手紙6章1~11節(p28以下)。
さらにパウロが、このガラテヤ書を書かねばならなかった歴史的背景について少し触れておきましょう。ガラテヤ書1章6節でパウロが、ガラテヤ教会がキリストの恵みへ招いてくださった方から離れて、キリストの福音をくつがえす教えに乗り換えようとしていると嘆いています。それはどういうことだったのでしょうか。
研究者たちの推定では、この手紙は紀元50年代の中頃に書かれたとされています。紀元49年にローマ皇帝クラウディウスは、使徒言行録18章にあるようにユダヤ人をローマから追放しました。それはユダヤ教会の内部でキリストの福音が広まるにつれて騒動が起こり、ローマ当局はキリスト教徒を追放する策に出たと考えられています。つまりユダヤ教会が安定しておれば、ローマ当局も管理能力を認め、その存在と活動を許していた。そのような権力の宗教管理は、ローマの支配の及ぶところではどこでも行われていたと考えられます。ローマから数千キロも離れているガラテヤであっても、安定したユダヤ教会であれば認められ、他方キリスト教会は騒動を起こすということで警戒されていたと思われます。
ガラテヤ教会は、パウロのいうようにキリストの福音から始まりました。しかしその信仰を保ち続け、また拡げていくのは、権力の監視や世間の無理解のもとでは困難を極めたと言えましょう。そのためでしょうか教会は、できるだけ安全なユダヤ教会の形や教えに近づこうとします。それを見抜くパウロは、嘆き怒ります。3章3節でこう言います。「あなたがたは霊によって始めたのに、肉で仕上げようとするのですか。」パウロにとって霊の出来事とは、イエス・キリストがパウロと共に死んでくださったことであり、共に復活してくださったことです。それが教会の基本であるのに、肉、つまりユダヤ人であることの徴(律法)、具体的には割礼や食物規定の教えを再び取り入れ、ユダヤ教に戻ろうとするのか、とパウロは嘆きや怒りの言葉を投げかけます。私たちはそれをこう言い替えましょう。「あなたがたは福音で始めたのに、ほかの福音つまり律法で仕上げようとするのですか。」
このパウロの怒りといってよいほどの問いかけには、アンティオキア教会で起こったある事件が背景にあります。パウロは、かつてアンティオキア教会でペトロのとった態度を厳しく非難したことがありました。すでにアンティオキア教会は、イエス・キリストの福音のもとに、ユダヤ人や異邦人など多様な民族や人種が混じり合う群れでした。ある時、みんなで食事をしているところにユダヤ教主義者が入ってきた。するとユダヤ人ペトロはユダヤ教主義者の目を気にして態度を変え、ユダヤ式に振る舞い始め、教会の交わりのしるしである食事会を気まずいものにしてしまった。しかしアンティオキア教会はキリストの福音に立つ教会としてユダヤ主義から解放されていて、異なる民族や人種であっても共存することができていたのに…。パウロはかねがね5章1節のように語っていたのでしょう、「キリストは私たちを自由の身にしてくださったのです。だからしっかりしなさい。奴隷の軛に二度とつながれてはなりません。」ここで自由とは、それぞれの民族や人種が持っている伝統や文化、習慣や考え方に縛られている奴隷状態からの解放を意味します。
以上のようにパウロは、アンティオキア教会の事件を思い起こしながら、同じような道をたどっているガラテヤ教会に対しても怒りをぶつけるのです。確かにパウロの言葉は正しい。しかしそれが正しければ正しいほど、だれがそれに耐えることができるでしょうか。実はパウロ自身もそれを自分に対する問いかけでもあると心得ています。ですからけさのテキスト15節以下を読むとき、パウロの厳しい言葉は、自らもその仲間であるガラテヤ教会に対して、律法的に追いつめるのではなく、キリストの愛と福音を語ることであったのです。
戦時中の教会について少しお話しして終わりたいと思います。
明治以降、近代国家を創るために日本政府がとった宗教政策は、天皇家の宗教である皇室神道を国教と定め、全国各地にあった神社をその支配下に組み入れました。さらに他の教派神道、仏教、キリスト教、新興宗教などのすべての宗教を、国教に逆らわない限り、存在と活動を認めました。キリスト教の場合、大正天皇が亡くなったのが12月25日、教会はクリスマスを自粛し祝うことができませんでした。戦争が始まる直前、すべての教派は意に反して合同させられ、その代表者が天皇家の神が祀られている伊勢神宮を参拝しました。戦時中の礼拝では皇居に向かって天皇を礼拝し、君が代を歌いました。そのようにして日本の教会は自らを守ろうとし、生き残ろうとしました。
もしそれをパウロが見たら、どう言うでしょうか。「それはアンティオキア教会やガラテヤ教会と同じではないか。霊で始めたのに肉で仕上げようとするのか。キリストの福音から始めたのに、異なる教えで仕上げるのか」と。しかしパウロは、そのように厳しく責めながらも、ガラテヤ教会を切って捨てなかったように、日本の教会も切り捨てないでしょう。パウロは、イエス・キリストの誠実・信実がガラテヤ教会にあり、キリストがそこにおられると信じていたように、日本の教会に対しても同じ言葉を投げかけるでしょう。「この自由を得させるために、キリストはわたしたちを自由の身にしてくださったのです。だから、しっかりしなさい。奴隷の軛に二度とつながれてはなりません。」
私はかねてより、日本に住んでいる外国人の問題にかかわってきました。日本バプテスト連盟の日韓在日特別委員会の働きには、委員会の創設以来40年間、関わっています。そこでは、この国に住む外国人の人権問題をテーマにしてきたのですが、そういう運動を通じて、この日本は一つの民族や人種ではなくて、多種多様な民族や人種の集合体であることがわかってきました。さらにこの国がさらに続くのであれば外国人をどんどん入れ、共に生きていかねばなりません。すでにこの国は、天皇を象徴とする単一統合国家から、いろいろな多様な民族や人種が共に生きる国に移らざるを得なくなっているといえます。私はこの運動に関わるようになって、パウロの置かれた世界と、そこで考え抜かれた信仰の言葉が心に響くようになりました。
最後に、ガラテヤの信徒への手紙の最後にあるパウロの言葉を読み、ガラテヤ教会への愛と祝福を、私たちへの愛と祝福として受け取りたいと存じます。
ガラテヤの信徒への手紙6章11節以下(新共同訳p350以下)。